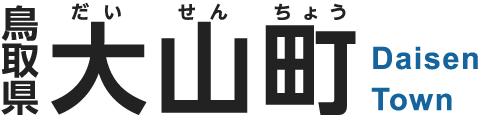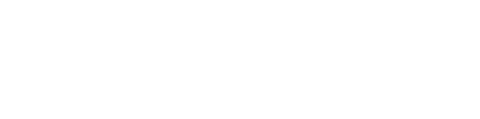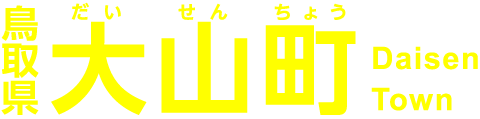鉄燭台(二基)
更新日:
2020年05月15日


(写真左 天文十九年銘 写真右 天文二十二年銘)
ロウソクをともす灯火台である燭台は、灯盞(とうさん)に油を入れ灯心に灯をともす灯台よりも遅れて、中世以降に普及したものです。この燭台は大山寺において、仏前で香・華・灯を供養する香炉・花瓶・燭台の組み合わせ(三具足、五具足という)で用いられていたものが現在まで伝えられたものです。
鉄を鍛えてつくった燭台で中世に遡るものは、全国的にみても非常に少なく、東北地方に若干例があるだけです。大山寺の燭台は東北の事例とはまったく形式が異なり、近世に普及する燭台の先駆例といえる形式のもので、西国に伝わるめずらしい例として工芸史的な意義がきわめて大きいものです。
また、竿部には具体的に使用場所(寄進先)が銘に記されており、中世大山寺の状況を知るための一次資料として価値の高いものといえます。
| 指定日 | 平成27年9月11日 |
|---|---|
| 種別 | 美術工芸品 |
| 所在地 | 大山町大山(大山寺宝物館霊宝閣内) |
お問い合わせは商工観光課 文化財室
大山町役場大山支所 1階
〒689-3332 大山町末長500
〒689-3332 大山町末長500
電話0859-53-3136